式内社「簀原神社」が始まり
9世紀中頃に、式内社「簀原神社」として創建された。
12世紀初頃に、桂川の洪水により流失し、跡地(現在地)に簀原(すはら)大明神を祀る。
13世紀頃に、乙訓坐大雷神社と改名する。
16世紀に、菱妻神社に変更される。
簀原(すはら)とは
「簀原」は、葦(ヨシ)の群生地としての「原」のこと。
なお、「葦」は湿地や水辺に生育する多年草のこと。
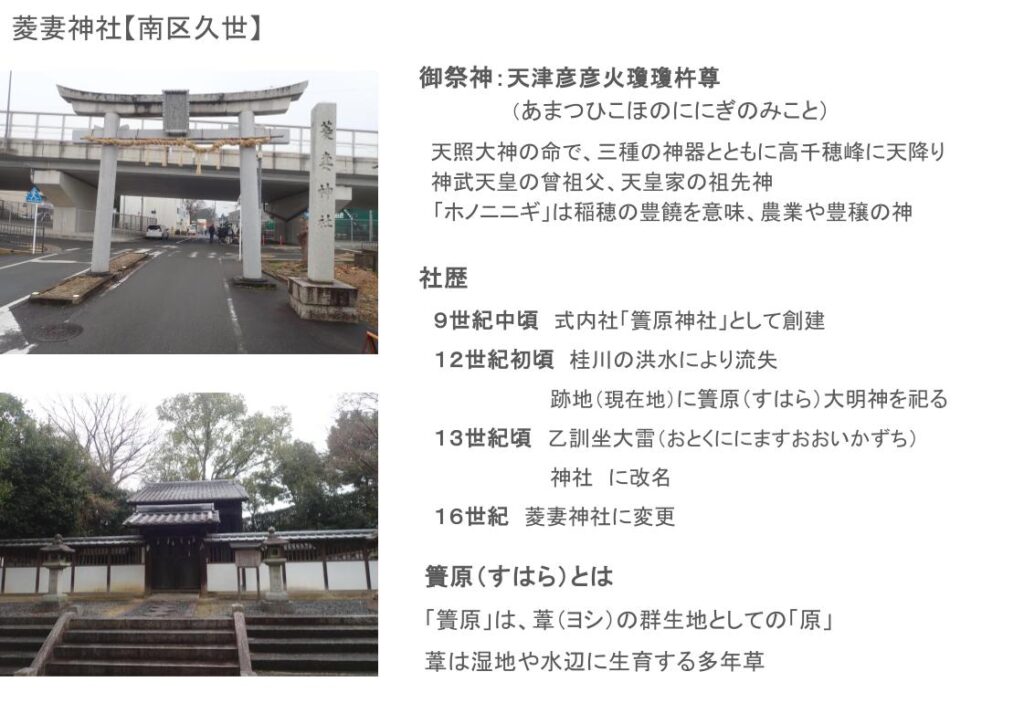
 神社
神社9世紀中頃に、式内社「簀原神社」として創建された。
12世紀初頃に、桂川の洪水により流失し、跡地(現在地)に簀原(すはら)大明神を祀る。
13世紀頃に、乙訓坐大雷神社と改名する。
16世紀に、菱妻神社に変更される。
「簀原」は、葦(ヨシ)の群生地としての「原」のこと。
なお、「葦」は湿地や水辺に生育する多年草のこと。
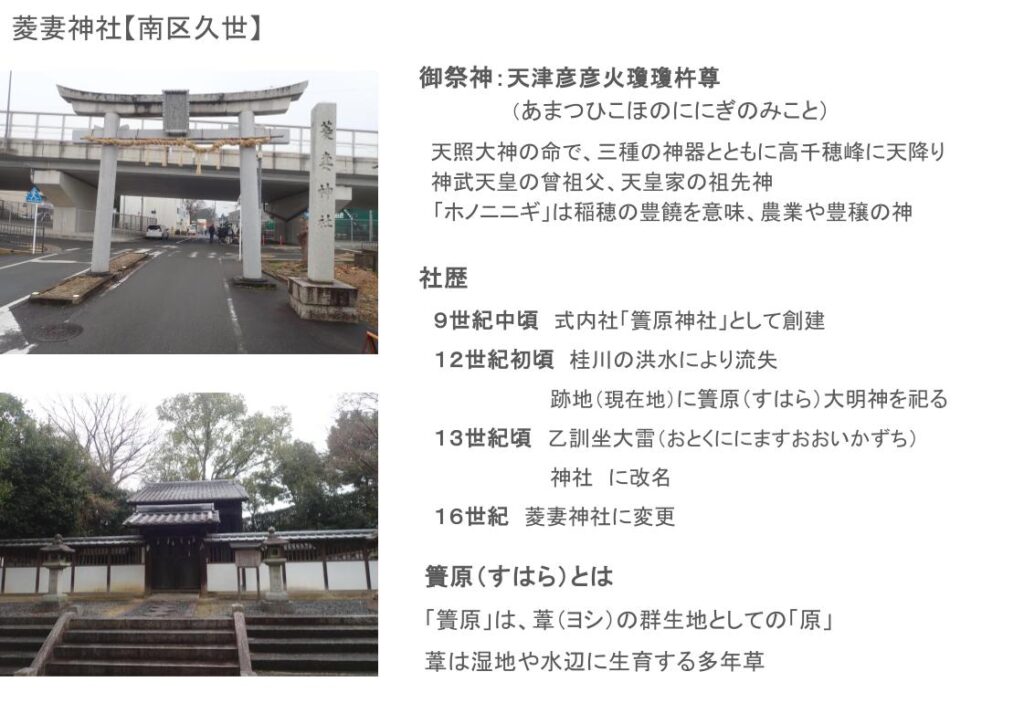
コメント